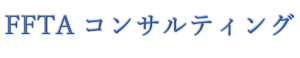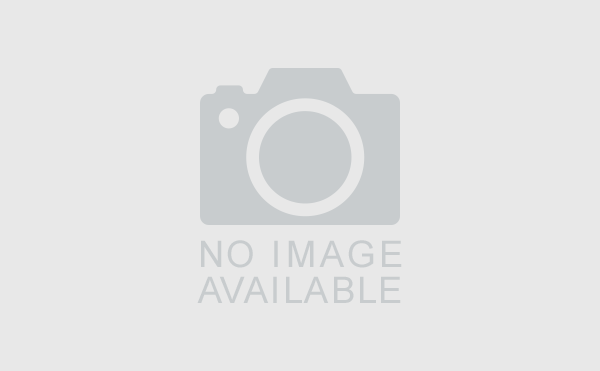検認?事後確認?経産省と財務省で異なるEPA/FTAの用語
EPA(FTA)を利用者を混乱させている一つの要因は、経済産業省と財務省・税関の使用する用語の違いです。
原産地証明書の内容が正しいかどうか輸入後に税関が調査を行うことを英語では「verification」といいますが、日本では「検認」と「事後確認」の2種類の用語が使用されています。
意味は殆ど一緒ですが、異なる点もあるので確認しておきましょう。
検認
「検認」は経済産業省と日本商工会議所が使用しています。経済産業省は第三者証明と認定輸出者に係る原産地証明を所管しています。日本商工会議所又は認定輸出者が発行したEPAの原産地証明書について輸入国税関からの調査のことを「検認」と呼んでいます。
事後確認
「事後確認」は財務省・税関が使用しています。財務省・税関はEPAを利用した輸入について通関後に原産地証明の内容が正しいかどうか調査を行っています。また、CPTPPや日EU・EPA等の自己申告制度を利用して輸出者又は生産者が発行した原産地証明書について輸入国税関の求めに応じて調査に協力することとなっています。これら税関が行う調査を輸出・輸入に拘らず「事後確認」と呼んでいます。
経済産業省は輸出の自己申告について一定の関与が認められていますが、主体は財務省となります。
「事後確認」と「事後調査」
税関は輸入申告の内容が正しいかどうか輸入後に調査を実施する「事後調査」を行っています。EPAに特化した調査を「事後確認」と称することとして「事後調査」と区別したものと思われます。税関が実施する輸入後の事後確認については、関税暫定措置法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に基づき行われます。また一般特恵関税(GSP)については、関税暫定措置法第8条の4の規定に基づき実施されます。これに対し、輸入事後調査は関税法第105条に基づき実施されています。「事後確認」と「事後調査」では、根拠法令が異なるので、異なる用語を使用する必要があったものと考えられます。
税関が「検認」を使用しない理由
「事後確認」は、平成30年4月1日以降に新たに実施されることとなったもので、「検認」よりも新しい言葉です。
「検認」とは、「検査してから認定、認証すること。」(精選版 日本国語大辞典)とされています。事後確認で非違が見つかれば追徴(多くの場合、修正申告の慫慂と加算税の賦課)を行うこととなり、単に「検査してから認定、認証すること。」に留まりませんので、税関としては、経産省が使用している「検認」という用語を使用しなかったのだと筆者は考えています。
「検認」と「事後確認」の使用場面まとめ
「検認」と「事後確認」の使用場面を纏めると下記の通りとなります。
| 原産地証明書の種類 | 第三者証明・認知輸出者 | 自己証明 | |
| 輸出 | 用語 | 検認 | 事後確認 |
| 日本の実施主体 | 経済産業省・日本商工会議所 | 財務省・税関 | |
| 根拠となる法律 | 経済連携協定における特定原産地証明に関する法律 | 経済連携協定における申告原産品に係る情報提供等に関する法律 | |
| 輸入 | 用語 | 事後確認 | |
| 実施主体 | 財務省・税関 | ||
| 根拠となる法律 | 関税法、関税暫定措置法 | ||
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*日本商工会議所に提出する対比表を作成したいが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。