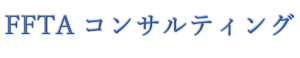EPA(FTA)に関する帳簿・書類の保管の義務は各EPA協定に定められていますが、保存の期間は協定によって異なります。輸入の場合は、協定の規定にかかわらず、関税法の規定により輸入の日から5年間です。
これらの書類は、税関の事後確認(検認)、事後調査の際に必要な証拠書類となります。
目次
輸入者
関税法第94条により品名、数量、価格、仕出人の名称、輸入許可年月日、許可番号を記載した帳簿は7年間、仕入書、契約書、運賃明細書、保険料明 細書、包装明細書、価格表、その他輸入申告の内容を明らかにすることができる書類は5年間保存することが義務付けられています。EPAの原産性に関する書類を輸出者から入手している場合、輸入者による自己証明を行った場合でも、これらの書類は関税法に規定する「その他輸入申告の内容を明らかにすることができる書類」に該当すると考えられるため、利用したEPAの規定にかかわらず輸入の日から5年間保存しておきましょう。
関税法基本通達の規定
関税法基本通達68-5-11 の4(原産品であることを明らかにする書類の取扱い)には、EPAを利用した際に税関が輸入者に求める書類が例示されています。
完全生産品(WO)
契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等(当該産品が各協定に基づいて完全に得られた、又は生産された産品であることを確認できるものに限る。)
原産材料のみから生産される産品(PE)
契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入記録、製造原価計算書、仕入書、価格表等(ただし、全ての一次材料(産品の原材料となる材料をいい、当該原材料の材料を除く。)が各協定に基づく原産品であることを確認できるものに限る。)
関税分類変更基準(CTH)
総部品表、材料一覧表、製造工程フロー図、生産指図書等(全ての非原産材料の関税率表番号が、適用する協定の品目別規則に応じた水準で確認できるもの)
付加価値基準(VA)
製造原価計算書、仕入帳、伝票、請求書、支払記録、仕入書、価格表等(適用する協定に定める計算式によって、特定の付加価値を付けていることが確認できるもの)
加工工程基準
契約書、製造工程フロー図、生産指図書、生産内容証明書等(当該基準に係る特定の製造又は加工の作業が行われていることが確認できるもの)
輸出者(製造者)
EPA協定では、特定原産地証明書の発給機関に証明書の発給を申請した者、自己証明を行った者に対して、3年~5年の間、原産性を証明する書類の保管を 義務付けています。なお、日EU・EPAは、輸出者に対し4年間の書類の保存を義務付けています。
| 5年間保存義務が課されている協定 | 3年間の保存義務が課されている協定 |
|---|---|
| 日メキシコ協定 、日マレーシア協定 、日チリ協定 、日タイ協定 、日インドネシア協定 、日フィリピン協定 、日インド協定 、日ペルー協定 、日オーストラリア協定 、日モンゴル協定、CPTPP | ブルネイ協定 、日アセアン協定 、日スイス協定 、日ベトナム協定、RCEP |
どのような書類を保存するかについては、経済産業省ホームページの「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」及び上記の関税法基本通達の規定を参考にするとよいと思います。
また、本ホームページの「EPA原産品申告書(自己証明書)の作成方法」の「Step4 事後確認に備えた証拠書類の作成」をご参照頂ければと思います。
日EU・EPAでは、協定で保存すべき書類が規定されていますので注意しましょう。EUにおいては、輸入後もEPA税率の適用の申請を行うことが出来ますが、その場合においても、書類の保存義務は原産品申告書(自己証明書、自己申告書)の作成の日から5年間となります。輸入後1年以上経てから関税の還付申請を行う場合など、税法上の書類の保存義務の5年間を超えて保存する必要がある場合もありますので注意しましょう。
サプライヤー証明書
原材料の供給者からのサプライヤー証明書に基づき証明を行っている場合は、輸入国税関からサプライヤー証明書の根拠資料の提示を求められた場合、提示しなければEPA税率の適用を否認される恐れがあります。従って、サプライヤー証明書の根拠となる書類についても保存をしておくようにサプライヤーに要請しておく必要があると考えられます。
EPA税率の書類の保存義務は、原産地証明書発行の日又は原産品申告書作成の日から起算されることとなります。サプライヤー証明書は、それらの証明書の根拠となる書類ですので、その起算日を基に、サプライヤーに書類の保存を要請しておく必要があります。場合によっては、協定で定められた期間を大きく超えて長期間の保存を要請する必要がある場合も想定されます。
貴社の原産地証明書に間違いはありませんか?
間違ったHSコードに基づき日本商工会議所から特定原産地証明の発給を受けている場合、輸入国税関の事後確認(検認)によりEPA(FTA)税率の適用が取り消され、貴社の信用が失墜することは勿論、輸出先から損害賠償を提起される恐れがあります。
貴社の証明に誤りが無いかどうか確認してみませんか?
HSコードのプロがお手伝い致します。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。