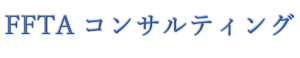自己証明は、十分な知識がなくても簡単に原産品申告書(原産地証明書)を作成することができので、第三者証明に比べてリスクが大きくなると考えられます。そのリスク対応策について考えてみたいと思います。
目次
自己証明利用時特有のリスク
第三者証明の場合は、税関の事後確認(検認:verification)や事後調査で、EPA税率の適用が否認され追徴を受けるということは、それ程高い確率で発生しているわけではありません。完璧ではないにしても、公的な第三者が産品が原産地規則を満たしているか否かをチェックして証明するという機能を果たしている証拠だと思います。
ところが、日EU・EPAやCPTPPのように自己証明になると、輸出者(製造者)に十分な知識がなくても簡単に原産品申告書(輸出入者自らが作成する原産地証明書:自己申告書)を作成することができます。しかも、第三者のチェックを受けていないことから、税関の事後確認等において原産地基準を満たしていないことが判明するリスクはかなり大きくなると想定されます。
そのリスクを回避する最善の方法は、輸入者が輸出者から原産地基準を満たしていることの証拠書類を入手し、出来れば、輸出者側の工場に赴いて原材料及び製造工程の確認を行うことです。このことはこれまでの第三者証明においても重要なことでしたが、自己証明においては、輸出者がいい加減な証明書を作成することを回避するという観点から、一段と重要となってくると考えています。
しかしながら、輸出者から企業秘密等で情報開示できないと言われることも多いと思います。このような場合、輸出者が十分な根拠がないままに原産品申告書を作成したり、税関の事後確認に際して対応を怠ったりするような事態を回避するにはどうすればよいか、輸入契約を締結する際に十分に考える必要があるのではないかと考えています。
文書による事前教示の活用
EPAを利用する上で一番のリスク回避策は文書による事前教示の活用です。税関ホームページに詳しい利用方法が掲載されていますのでご参照ください。
文書による事前教示では次のようなメリットがあります。(日本への輸入の場合。)
- 税関が発出した回答文書の内容については、発出後最長で3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いの変更があった場合等を除く)
- 輸入時に原産品申告明細書等の関係書類の提出免除されます。
- 税関から原産地証明に関する質問・事後確認を受けるリスクが低い。
当コンサルティングでも文書による事前教示関係書類の作成支援のサービスを行っていますのでご相談ください。
生産仕様書等で使用原材料・原料調達先を明示する
品目別規則の関税分類変更基準を用いる場合で、全ての原材料を非原産材料と見做して原産地基準を満たしていることを証明できる場合は、原料調達先を指定する必要はありません。
しかし、原産材料を使用していることを証明に利用している場合や品目別規則で使用原料に制限がある場合には、当該原材料の調達先を輸入契約書若しくは生産指図書、生産仕様書等で指定しておくことは有効なリスク回避手段です。税関の事後確認や輸入事後調査の際には、原料調達先を指定した生産仕様書等を提示することにより、多くの場合は調査終了となるでしょう。万が一、生産者が契約に従わずに品目別規則を満たさない原材料を使用していた場合は、契約違反ということで、追徴関税や加算税等の追加費用の賠償を請求することも容易になると思います。
ここでの注意点は、調達先の企業を指定するのではなく、原材料の生産工場や生産地(収穫地)を指定すべきということです。
税関が発表している輸入非違事例に、日EU・EPAのパスタ(第19.02項)の事例があります。この場合、非原産の穀粉は10%を超えないことが必要とされています。この事例では、非原産の小麦粉が10%以上使用されており、品目別規則を満たさないことが判明しました。できれば小麦粉のEU域内の生産農場を明示するとともに、輸出者には、生産地が明確に記載された生産証明書等を保管してもらっておきましょう。
(注)第11.01項の品目別原産地規則は、第10類の全ての材料が完全生産品であることとなっています。
輸出者(証明者)の義務を明確にする
企業秘密等の理由により輸出者(生産者)からEPAの原産地証明に関する十分な情報が得られない場合、自己証明においては輸出者等が本当に原産地基準を満たしていることを確認したのかどうか検証する手段がないことから、EPAの利用に関して輸入者は大きなリスクを負うこととなります。そのリスクを回避するためには、可能な場合においては、原産品申告書(EPAの原産地証明の自己申告書)を発行する者に以下に示すような義務がることを輸入契約書等に明記しておくべきではないかと考えています。
税関事後確認への対応
日EU・EPA、CPTPP等の自己証明制度のEPAを利用した輸入申告の際には、原則、原産品申告書、原産品申告明細書とその根拠となる原材料表等を税関に提出することとなっています。企業秘密等により輸出者から原産品申告明細書を作成するための情報を入手できないときは、その旨を原産品申告明細書に記載したり、或いは、日EU・EPAの場合は、その旨をNACCSに入力することにより、添付を省略することが可能です。
しかし、関税法基本通達68-5-11 の4(原産品であることを明らかにする書類の取扱い)には、「この場合において、関税暫定措置法基本通達12 の2-2に規定する原産品であるかどうかの確認の実施を検討する必要があるので留意すること。」とあり、原産品申告明細書を提出した場合に比べて税関から事後確認を受ける確率は飛躍的に高くなると考えられます。税関から問い合わせがあった場合には直ぐに資料を提出できるように輸出者等に要請しておきましょう。
輸入契約には、税関の事後確認があることを前提に、次の事項を規定しておくことが望ましいと考えています。
- 税関の事後確認に対応すること
- 日EU・EPAの場合は、輸入者を通じた問合せ(この場合は、直接輸入国税関へ回答することが出来る。)及び輸出国税関からの調査への対応
- CPTPPの場合は、輸入国税関からの問合せ又は調査への対応
- 日米貿易協定の場合は、輸入者からの要請により必要な情報を輸入国税関に提供すること
- 税関の事後確認に対応しなかったため又は税関からの問合せ等に対して期限内に回答できなかったために、税関からEPA税率の適用を否認された場合は、追徴税額等の補償を行うこと
証拠書類の保管
輸出者等が、原産品申告書を作成する際に使用した原産地基準を満たしていることを証明する書類を、協定が定める期間保管しておくことを規定しておく。
日米貿易協定の場合は協定に書類の保管義務が規定されていないため、日本の関税法の規定に合わせて輸入の日から5年間輸出者も証拠書類を保管することを定めておきましょう。
原産地基準を満たすことを証明できなかった場合の対応
税関の事後確認により、輸出者等が産品が原産地基準を満たしていることを証明できなかったためにEPA税率の適用を否認された場合は、追徴税額等の補償を行うことを規定しておくべきでと考えます。
なお、原産地基準を満たしていることを証明できなかった場合には、原産地規則の適用を誤っていた場合の他、原産地規則を満たしていることを証明する必要な書類を税関に提示できなかったことも含まれますので留意してください。
原産地基準を満たさないことが判明した場合の対応
調達先や製造工程の変更等で原産地基準を満たさなくなった場合、又は、原産性の判定が誤っていたことが判明した場合は直ちに連絡してもらえるように規定しておきましょう。
誤った原産品申告書で通関しても、事後確認や事後調査が行われる前に税関に連絡して修正申告を行えば、関税等の追徴はあるものの、加算税等のペナルティーが発生することは避けられます。
自己証明制度利用時のリスク回避策(まとめ)

自己申告の原産地証明書作成のアドバイス
これまでの日本商工会議所が発給する特定原産地証明書と異なり、日EU・EPAやCPTPPの原産品申告書では、第三者によるチェックがありません。
誰でも簡単に作成できますが誤った原産品申告書の作成した場合は、損害賠償のリスクや顧客からの信用失墜など大きなリスクがあります。
原産品申告書の作成に必要な根拠資料の作成から輸入国税関の調査に備えた書類の保存迄、初歩から丁寧にアドバイスいたします。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。