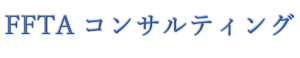EPA(FTA)の積送基準(日EU・EPAの場合は「変更の禁止」)とは、貨物が輸入国に到着するまでに原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準です。次のいずれかの条件を満たす場合は、産品は原産品としての資格を保持すると認められます。
- 直送されること。
- 第三国を経由する場合は、税関の管理下に置いて、積替え、一時蔵置及び産品に実質的な変更を加えない程度の作業のみが許される。
積送基準を満たしていることの証拠書類として、どのような書類が必要か見ていきます。
なお、日EU・EPAではEU域内、CPTPPではCPTPPの締約国間では積送基準の適用はありません。
目次
直送B/L
輸出国から輸入国へ積替えなして無しで運送される場合は、途中で物品に変更が加えられることはありませんので、B/Lが積送基準を満たすことの証拠書類となります。
第三国を経由したEPAの利用(運送要件証明書)
輸出国から輸入国への運送の際に第三国を経由した場合には、税関に途中で貨物に変更が加えられていないことを証明する「運送要件証明書」を提出する必要があります。これらには次のようなものがあります。
通しのB/L
フォワーダー等が発行する輸出国から輸入国までの通しのB/Lです。例えば、RCEPを利用して上海から釜山で積替え、新潟港まで輸送するような場合に、通しのB/Lを発行してもらいます。
税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書
税関その他の権限を有する官公署(例えば、港湾管理者)が、積替え時に保税地域において貨物に変更が加えられたいないことを証明する書類(非加工証明書)を発給した場合には、この書類が「運送要件証明書」となります。税関その他の権限を有する官公署がこのような証明書を発給する国は多くないので、事前の確認が必要です。
「その他税関長が適当と認める書類」
通しのB/Lや権限のある当局の非加工証明書が入手できない場合には、次のような方法が考えられます。
原産地証明書に経由地を記載してもらう方法
日本への輸入の際しては、運送上の理由等により通しのB/Lを利用できず、締約国でない国を経由して運送される場合、特定原産地証明書に積替え地等の記載を行うことがにより、積送基準の証明と認められる取扱いとなっています(関税法基本通達68-5-1(1)ハ 非原産国における積替え等に関する確認)。
例えば、カンボジアからベトナムのホーチミン港までまでトラックで輸送し、ホーチミン港で船積するような場合、カンボジアの当局が発給する特定原産地証明書に、ホーチミン港を経由する旨記載してもらいます。
その他の場合
日本では、以下の書類が必要とされていますが、用意した書類が条件を満たしているか事前に税関に確認したほうが良いと思われます。
- 原産国から日本への貨物の流れや貨物の同一性を確認するための原産国から第三国、第三国から日本への運送関係関連書類(船荷証券等)
- 第三国で積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされていないことを証明するための倉庫の管理責任者等による非加工の証明書類
- 税関の監督下にある保税地域への搬出入記録
自己申告を採用しているEPA
日EU・EPA及びCPTPP等の自己証明では、第三者証明の場合と異なり、「税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書」の提示が求められることはありません。しかし、日本への輸入の際には上記と同様、第三国での作業が税関の管理下に置かれていて、積替え、一時蔵置及び産品に実質的な変更を加えな程度の作業しか行われていないことを証明する書類を提出する必要があります。輸出の場合は、輸入国の税関によっては、輸入時に書類の提出を求められないこともありますが、その場合でも、証拠書類、帳簿等を保管しておく必要があります。
何れ場合にも、用意した書類が積送基準を満たす書類として認められるか事前に税関に確認を行った方が良いと考えます。
連続する原産地証明書(back-to-back)
RCEP及び日・アセアン包括協定では、通常の原産地証明書発給に加えて、一の締約国(締約国A)の原産品が、別の締約国(締約国B)を経て更に別の締約国(締約国C)に輸入される場合に、締約国Bにおいて貨物に対して何ら加工がなされず、締約国Aで得た原産資格に変更がない場合に、締約国Aで発給された「最初の原産地証明書(original CO)」に基づき、締約国Bにおいて「連続する原産地証明書(back-to-back CO)」の新たな発給を受けることができます。
この規定により例えばタイ産の貨物をシンガポールでストックし、日本に輸入する場合に、上記の「その他税関長が適当と認める書類」を提出するのと比べて、簡単な手続きでEPA(日・アセアン協定に限る。)を利用することが出来、保税地域での保管も義務付けられていません。
ただし、バック・ツー・バックの原産地証明書は発効しないとしている国があるので注意が必要です。日本商工会議所は、RCEPのback-to-backの原産地証明書は発給するとしているものの、日・アセアン包括協定のバック・ツー・バックの原産地証明書は発効しないとしています。詳しくはこちら

「EPA(FTA)税率の適用を受けるための要件」に戻る
EPA/FTA原産地証明のコンサルティング
*日本商工会議所に提出する対比表を作成したいが、原材料のHSコードが分からない。
*輸入国税関から問い合わせが来たが、どのように対応したらよいかわからない。
初歩の初歩から対応いたします。
是非、HSコードのプロにお任せください。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。