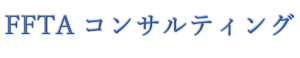EPA(FTA)の関税分類変更基準(CTC:Change in Tariff Classification)とは、産品のHSコードと使用された全ての非原産材料のHSコードの間に協定で定められた変更が生じた際に、協定上の「原産品」として関税が優遇されることとなる基準です。
原産地証明を行う際の注意事項についてみていきたいと思います。

目次
- 関税分類(CTC)の種類
- 協定により原産地基準が異なる事例
- 関税分類変更基準(CTC)の優位性
- 関税分類変更基準(CTC)を採用した場合の根拠資料
- 原材料表(対比表)の作成に当たって注意すべきこと
- 製造工程表の作成に当たって注意すべきこと
関連記事
- 成分表を基に原産地証明は出来ない
- 化学品のEPA(FTA)の原産地証明根拠資料作成の注意点
- 機械類の原産地証明の注意点
- EPA・FTAの原産地証明と機械類部分品分類5原則
- EPA・FTAの原産地証明と自動車の部分品分類5原則
関税分類変更基準(CTC)の種類
関税分類変更基準には、次の3種類があります。
- 類変更基準(Change of Chapters:CC):産品と全ての非原産材料の間にHSコードの上2桁(類)の変更があった場合に「原産品」となる。
- 項変更基準(Change of Tariff Headings:CTH):産品と全ての非原産材料の間にHSコードの上4桁(項)の変更があった場合に「原産品」となる。
- 号変更基準(Change of Tariff Sub-headings:CTSH):産品と全ての非原産材料の間にHSコードの上6桁(号)の変更があった場合に「原産品」となる。
一般に類の変更は産品の性質が大きく変わりますが、通常、号が変更となっても大きく性質は変化しません。従って、類変更基準が最も厳しい基準で号変更基準が最も緩い基準になります。
類変更基準(CC)
類変更基準は食品等によく使用されている基準です。
EPAの締約国において産品を製造する場合において、生産に使用される全ての非原産材料のHSコードと産品のHSコードの間に上2桁のコード(類)の変更が生じた場合に、産品が当該EPAにおいて原産品となるという基準です。
一般に、原則として項変更基準(CTH)を採用している非特恵原産地規則よりは厳しい基準となります。
【例】胡瓜及び食酢から胡瓜の酢漬けの製造(日本からの輸出)
日EU・EPAの第20.01項の品目別規則はCC(類変更)です。胡瓜(第7類)と食酢(第22類)から胡瓜漬(第20類)を製造する場合、胡瓜も食酢も中国から輸入し、日本で胡瓜漬を製造した場合も原産地基準を満たすことになります。

一方、日・タイEPAでは、第20.01項の品目別規則はCC(類変更)となっていますが、第7類からの変更は除外されています。日・タイEPAを利用するためには、胡瓜は日本原産品(即ち日本で収穫された胡瓜)を使用する必要があります。 *HS品目表については、こちら(輸出統計品目表)をご覧ください。
項変更基準(CTH)
最もよく使用される基準です。
EPAの締約国において産品を製造する場合において、生産に使用される全ての非原産材料のHSコードと産品のHSコードの間に上4桁のコード(項)の変更が生じた場合に、産品が当該EPAにおいて原産品となるという基準です。
日本の非特恵原産地規則や一般特恵関税(GSP)の原産地規則も原則CTHですし、日・アセアンEPA、日・スイスEPA、日・ベトナムEPAの一般規則もCTHとなっています。
【例】天然コルクから天然コルクの栓の製造(日本からの輸出)
日EU・EPAの天然コルクの栓(第4503.10号)の品目別規則はCTH(項変更)です。
海外から天然コルク(第4501.10号)を輸入し、ワイン用の天然コルクの栓(第4503.10号)を日本で製造した場合、第45.01項から第45.03項に変更となっているのでこの天然コルクの栓は日EU・EPA上の日本原産品となります。
天然コルク(4501.10) ⇒ 天然コルクの栓(4503.10)
号変更基準(CTSH)
第28類、第29類の化学品や、東南アジア諸国等の二国間EPAにおいて機械類でよく使用されている基準です。
EPAの締約国において産品を製造する場合において、生産に使用される全ての非原産材料のHSコードと産品のHSコードの間に上6桁のコード(号)の変更が生じた場合に、産品が当該EPAにおいて原産品となるという基準です。
一般に、非特恵原産地規則よりも緩い基準となっています。
【例】クエン酸及び水酸化ナトリウムからクエン酸ナトリウムの製造
日EU・EPAのクエン酸ナトリウム(第2918.15項)の品目別規則はCTSH(号変更基準)です。
輸入品のクエン酸(第2918.14項)及び水酸化ナトリウム(第2815.11号又は第2815.12号)を使用して日本でクエン酸ナトリウムを製造した場合には、日EU・EPAの原産地基準を満たすことになります。

協定により原産地基準が異なる事例
(事例1)
EPA原産地基準が非特恵原産地規則より厳しい場合
日・マレーシア協定では、粗製のパームオイル(第1511.10号)の品目別規則は「CC(第12類からの変更)」となっていますので、マレーシアにインドネシアから油やしの実 (第1207.10号)を輸入して粗製パームオイル(第1511.10号)を生産すると、油ヤシの実がマレーシア原産でないことからEPAの適用は認められません。
非特恵原産地規則は項変更で、かつ、原料に制限が付いていませんので非特恵原産地規則の項変更基準より厳しくなっています。この粗製パームオイルの非特恵原産地規則の原産国はマレーシアとなります。

また、日・アセアン協定及びCPTPPでは、CCとなっていますのでEPAを利用することが出来ます。
(事例2)
EPA原産地規則が非特恵原産地規則より緩い事例
第15.07項には、第1511.10号(パームオイルの粗油)及び第1511.90号(粗油以外のパームオイル、精製パームオイルが分類される)の2つの号があります。2つの号は搾油したままのものか、その後精製等の処理が行われているかの違いはありますが、同じパームオイルであることに違いはありません。
ここで、もし第1511.90号の精製パームオイルに号変更基準が採用されているとすれば、第1511.10号の粗製のパームオイルを精製しただけで協定上精製したた国の原産品と認定されるので非常に緩い原産地基準になります。
日・シンガポール協定と日・マレーシア 協定では第1511.90号(精製したパームオイルが分類される。)の品目別規則はCTSHです。同じパームオイルでも、粗製のものと精製したものでは、原産地基準に大きな差があります。

非特恵原産地規則は項変更で、項の変更が行われた最後の工程はインドネシアのC工場で行われているので、輸入申告時に申告する原産地はイン ドネシアとなります。EPAの原産地とは異なることになるので注意が必要です。
(事例3)包丁(第82.11項)の品目別原産地規則
品物によっては、類変更基準(CC)、項変更基準(CTH)及び号変更基準(CTSH)の全てが、日本が締結したEPAの何れかの協定に採用されている産品もあります。
例えば、第82.11項のナイフ、包丁の各協定の品目別原産地規則は次のようになっています。


第82類の物品の卑金属性の部分品は、汎用性の部分品(ボルト、ナット、リベット、コッター等)を除きその物品の属する項に属するとされています。従って、包丁(8211.94)の刃や金属製の柄(8211.95)は第82.11項に分類されますが、包丁とは別の号となります。従って、日マレーシア協定や日インドネシア協定ではCTSH(号変更)となっていますので、包丁の刃は必ずしも原産品である必要はないことになります。しかし、CC(類変更基準)やCTH(項変更基準)の協定では、刃や金属製の柄の部分については、原産品であることを証明する必要があります。
一番厳しい協定で原産地証明を行っておくと他の協定の証明を行う際に流用出来ますが、緩い協定で原産地証明を行っても、他の協定で利用できるとは限りません。
関税分類変更基準(CTC)の優位性
品目別規則に複数の原産地基準がある場合、使用する原産地基準を決定する必要があります。単発の輸出であればどの原産地基準を利用しても大きな違いはありません。まず、自社の知識で簡単に証明できる原産地基準を利用すればよいと考えます。
しかしながら、複数回にわたりに輸出する場合、関税分類変更基準を使用するすることは、一般的に他の原産地基準より優位性があると考えられます。
EPAの解説書・解説記事では、原産品申告書の作成者にどの基準を採用するかについて、優劣を付けることなく原産品申告書の作成者に委ねている場合が多いと思われます。当コンサルティングでは、後々の輸入国税関等による事後確認(検認)も想定して、下記の通り関税分類変更基準を第1選択肢として、原産地基準を決定していくことをお勧めしています。
付加価値基準(VA)との比較

原産地証明は、原則として、産品の輸出毎、生産ロットごとに行う必要があります。
しかしながら、産品の原材料は基本的に同一の物品を使用し、生産毎、輸出毎に変わることはありません。従って、原材料のHSコードも生産毎、輸出毎に代わることはなく、一度作成した関税分類変更基準を用いた対比表等の原産地証明に必要な資料は何度でも、同一のものを使用することが出来ます。使用原材料を変更した際に見直すことで足りると考えられます。
これに対し、産品のFOB価格や生産に使用する原材料の価格は、為替相場や原材料価格の変動により変化する可能性がありますので、付加価値基準は証明のメインテナンスが大変です。価格変動が少ない場合ですと一度作成した資料をそのまま用いていても特に大きな問題はないと思われますが、何れにしても定期的な見直しは必須です。価格変動が激しい場合は、輸出の都度、生産の都度見直しが必要な場合も考えられます。
加工工程基準(SP)との比較
加工工程基準も、関税分類変更基準と同様に、一般的に一度証明を行うと引き続き同一の証明が利用できると考えられます。ただし、説明に専門的な知識を要することが多く、税関職員もそのような専門知識は一般的には無いことが多いと思われることから、産品と原材料のHSコードを比較するだけの関税分類変更基準と比べ、説明資料の作成に時間が要することが考えられます。なお、一般の方には関税分類変更基準も十分に専門的かと思われるかもしれませんが、税関職員はその辺はプロですので、税関への説明の際に関税分類変更基準を用いて説明に苦労することは一般的にはないと思います。
関税分類変更基準(CTC)を採用した場合の根拠資料
経済産業省の「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」の資料には次のような根拠資料を保存しておくことを例示として示しています。
- 生産に使用した非原産材料(非原産と扱った「材料・部品」)のHSコードと、輸出する産品のHSコードが変更していることを示す資料
- 対比表【次頁参照】
- 対比表に記載された「材料・部品」で製造されたことを裏付ける資料
- 総部品表
- 製造工程フロー図
- 生産指図書
- 各「材料・部品」の投入記録(在庫「蔵入蔵出」記録) 等
- 「原産」と扱った「材料・部品」については、その原産性を示すための根拠となる資料
- 国内調達「材料・部品」については、その供給者(サプライヤー)からの情報
- 当該「材料・部品」が締約相手国原産品である場合は、輸入時の同協定に基づく原産地証明書の写し、当該「材料・部品」が原産品であることを示すその他の資料 (具体的には、後述の対比表や計算ワークシート)等
- 原産地証明書の写し、原産地証明書の発給を受けた輸出産品のインボイスや船荷証券等の船積書類の写し
対比表や製造工程表(製造工程フロー図)、生産指図書等は輸入国税関からの事後確認(検認)に備えて、英文のものを準備しておきましょう。
どこまで製造工程を遡って資料を作成すればよいか
製造工程が多数の部品、原材料、複数の工程を経て製造される場合、どこまで遡って証明すれば良いか迷われる場合もあると思います。
答えとしては、「原産地基準を満たすまで」とシンプルなものになります。
しかしながら、実際に証明しようとすると難しい事例もあると思います。判断に迷われる場合は 当コンサルティングにご相談ください。
原材料表(対比表)の作成に当たって注意すべきこと
関税分類変更基準を用いる際のEPAの原産性を証明する資料のうち、輸出する産品のHSコードと生産に使用した非原産材料(非原産と扱った「材料・部品」)のHSコードを一覧表の形にして対比させるようにした資料の事を、経済産業省及び日本商工会議所では「対比表」と呼んでいます。(対比表については、経済産業省及び日本商工会議所の資料をご参照下さい。)
FFTAコンサルティングがお勧めする簡便な原材料表
当コンサルティングでは、経済産業省や日本商工会議所の資料のような複雑な対比表を作成する前に、下記の表のようにまず、生産に使用する原材料の一覧表(総部材表)を作成し、その原材料の一つ一つにHSコードを当てはめていくことをお勧めしています。
日EU・EPAやCPTPPの自己申告の根拠資料としてはこのまま利用できますし、日本商工会議所から要求される対比表にも簡便に変換できます。

先ず全ての原材料・部品のHSコードを記載する
原材料表(対比表)を作成する際には、先ず生産に使用した全ての原材料・部品一覧表を作成し、それぞれの原材料・部品にHSコードを附していきます。
記載するHSコードについては、原則として4桁の番号を記載します。CTSH(号変更基準)の場合は、産品と同じ項に属する原材料については6桁(号)のHSコードを記載します。
CC(類変更基準)の場合は、日本の税関では2桁のHSコードを記載するだけで良いとしていますが、HSコード決定の単位は2桁の類ではなくあくまでも4桁の項のコードですので、HSコード決定のミスを避けるために、類変更基準でも4桁の項のコードを決定しておくことをお勧めしています。
全ての原材料のHSコードが関税分類変更基準準を満たしていればそれで証明は終了します。
原産地基準を満たさない原材料についてのみ、サプライヤー証明書の入手や僅少(許容限度)の規定の活用を検討します。経済産業省及び日本商工会議所の対比表の説明をそのまま適用して、最初から原産材料(日本製)であるか否かの判定を行おうとすると無駄な作業が多くなり、ミスも発生しやすくなると考えられます。
また、必要のないサプライヤー証明書をサプライヤーに要求することは出来る限り避けたものです。その意味では、僅少(許容限度)の規定を余裕をもって満足できるのであれば、サプライヤー証明書の入手よりも優先する方が望ましいと考えられます。
備考欄には、HSコード決定の裏付けとなる原材料の製品規格、部品番号及びその他の参考情報、また、サプライヤー証明書を活用する場合は、サプライヤーの名前、証明書の番号、製造工場名及びその住所、また、僅少の規定を利用する場合はその旨を記載しておきます。
対比表のHSコードは誤りが多い
関税分類変更基準を用いたEPAの根拠資料では、原材料表(対比表)の原材料に正しいHSコードを記載していくことが非常に重要ですが、これらに記載されているHSコードには多くの誤りがみられることがあります。原材料表のHSコードの誤りがEPAの否認に必ずしも直結するものではありませんので、原材料表(対比表)のHSコードの誤りに気付いていない輸出入者の方も多いのではないかと思われます。しかしながら、誤ったHSコードを放置しておくと、いつかは重大な事故につながりかねません。特に、機械類においては、EPA税率の否認に直行しかねませんので、注意が必要です。
誤ったHSコードを記載した対比表に基づいて日本商工会議所から特定原産地証明書を取得し、輸入国において原産性を否認された場合においても、日本商工会議所は責任を取ってくれません。それどころか、虚偽の証拠書類を提出したとして罰せられる可能性すらあります。(「EPA(FTA)の事後確認(検認)と事後調査」のページ参照)
また、日EU・EPAやCPTPP等の自己証明のEPAにおいても、虚偽の証明を行って原産品申告書を作成した場合には法律に基づき罰せられることがありますので、注意が必要です。
対比表の作成・確認については、当コンサルティングでも支援を行っていますので、是非お問い合わせください。
正しい対比表を作成するために必要なこと
HSコードに馴染みの無い輸出入者や製造者が使用原材料の一つ一つに正しいHSコードを付けていくことはなかなか難しいのではないかと思われます。各種のHSデータベースを利用することも考えられますが、このようなデータベースでカバーされない物品も多いと思われますし、データベースをうまく使用して正しいHSコードを付けるには、HSコードに関する詳しい知識が必要です。出来れば、HSコードに詳しいコンサルタントや通関業者(通関士)等、外部の専門家に依頼する方が安全と考えます。HSデータベースは、HSコードの見当をつける際には非常に有効ですが、データベースのみで最終決定を行うのは大きなリスクがあります。
通関業者に依頼する場合は、信頼のおけるHSコード(関税分類)に詳しい通関士のいる業者に依頼しましょう。通関士も普段扱っている品目ですと良いのですが、馴染みの無い品目ですとそれほど詳しくないので注意が必要です。
また、外部の専門家に依頼する際には、原材料の成分、スペック等、出来るだけ詳しい情報を提供するようにしましょう。品名だけですと、誤ったHSコードを付けられる原因となりかねません。HSコードは些細なスペックの違いで異なることがあるので注意が必要です。
防御的なEPA原産地証明の根拠資料を作成する
一つの物品に対してはただ一つのHSコードが対応すべきですが、しばしば不一致がみられます。(「HSコード(関税分類)の不一致が生じる理由」のページ参照)
しかし、不一致が生じそうな物品は予め想定がつきます。輸入国のHSコードの判断によっては原産性を否認される可能性がある場合には、防御的なEPA原産地証明の根拠資料を作成しておくことが望ましいと考えられます。このため、輸入国税関から原材料が関税分類変更基準を満たさないという指摘される可能性がある原材料について、以下の準備をしておくことが考えられます。
- 輸入国税関にHSコード或いは原産地基準を満たしているか否かを問い合わせる、出来れば拘束力のある事前教示を取得しておく
- 関税分類変更基準を満たさない恐れがある原材料を自社で生産している場合は、その物品が原産材料であることの証明資料を作成する。
- 他社で生産した原材料の場合はサプライヤー証明書を入手しておく。
- 僅少材料(許容限度)の規定を満たす場合には、価格資料を整えておく
原材料表には、必ずしも自社に不利となるHSコードを記載する必要はないと考えますが、どのHSコードを記載するにかかわらず、防御的な根拠資料の準備をしておくと良いと考えます。
関税分類変更基準(CTC) においても原材料の購買伝票は保管しておく
経済産業省の例示はあくまでも例示であり、原産性が証明できる資料があれば、必要のない資料もあるでしょうし、この例示にない資料も求められる可能性があります。
例えば、使用する原材料が会社提出の生産指図書通りのものが使用されているか否かを確かめるために購買伝票や会計資料の提示を求められる可能性があると考えられます。特に、自己申告等により輸入国税関から直接資料提示が求められる場合には、誤魔化しのきかない原資料に遡って調査されることがあると考えておいた方が良いと考えます。
元税関職員の立場からすると、生産指図書等は事後作成も場合によっては可能と思われますが、会計関係の帳票類は第三者も関与するのでより客観的な資料と考えられます。原材料の購買関係の資料は税務関係資料として保管されている資料と思われますが、税関から求められた際には提示できるようにしておくと良いと考えられます。
対比表作成の簡素化
対比表は、商品が異なればその一つ一つに対応して作成していく必要があります。品番が変わっただけで、原材料・部品のHSコードを一つ一つ確認して記載していく必要があります。原産地証明を行う商品が多くなると大きな負担となります。多数の部分品のHSコードの管理に悩まれている企業も多いと思います。
しかし、原材料・部品をある一定の基準でグルーピングしておくと、対比表の作成を簡素化することが出来ることがあります。簡素化の方法についてはノウハウが必要ですので、当コンサルティングにご相談ください。
製造工程表の作成に当たって注意すべきこと
原材料表(対比表) と並んで重要な資料が製造工程表(製造工程フロー図)です。製造工程表作成の目的は主として次の2点です。
- 原材料表に記載された原材料から原産地証明を行う産品が製造されていることを確認すること
- 製造が日本で行われたことを証明すること
原材料表(対比表)は製造工程表と整合性が取れている必要がある
原材料表(対比表) と製造工程表(製造工程フロー図)は別々の資料ではなく、完全に整合性が取れている必要があります。従って、原材料表に記載の無い原材料を使用することとなっていたり、原材料表にある原材料を使用していないような製造工程表は原産地証明の資料にはなりません。
そのことを十分理解して製造工程表と対比表を作成すれば「成分表を基に原産地証明はできない 」のページで述べたように、実際に使用していない原材料である成分表を基に原産地証明を行うことにはならないはずです。実際の製造工程表を基に原材料表(対比表)を作成するようにしましょう。
製造工程表には工場名及び住所を記載する
製造工程表には、物品を製造した工場名とその住所を記載します。2以上の工場で製造された場合には、それぞれの工場名と住所及びその工場で行われた製造工程が明確になるように記載します。
よく製造会社の本社の住所が記載されていることがありますが、それでは原産地証明の証拠書類にはなりません。製造工場を記載するのは、実際に物品が日本で製造されたことを証明するためです。
また、サプライヤー証明書で、製造場所として、サプライヤーの本社や事務所の住所、又は購入先の商社の名前が記載されていることがありますが、これも証明の資料にはなりません。
税関は、グーグルマップ等で実際に記載された場所に工場があることを確認することが想定されます。その際に、工場らしきものが無く、事務所のみ確認できる状態ですと、それだけで事後確認の対象とされてしまいかねません。
製造工程表は簡単なもので良い
原産地証明の根拠資料として詳細な製造工程表は必要ありません。ましてや、企業秘密に属するような情報や、QC工程図のような詳細な工程表は必要ありません。上記の目的を達成できれば簡単なもので良いのです。
貴社の原産地証明書に間違いはありませんか?
間違ったHSコードに基づき日本商工会議所から特定原産地証明の発給を受けている場合、輸入国税関の事後確認(検認)によりEPA(FTA)税率の適用が取り消され、貴社の信用が失墜することは勿論、輸出先から損害賠償を提起される恐れがあります。
貴社の証明に誤りが無いかどうか確認してみませんか?
HSコードのプロがお手伝い致します。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。