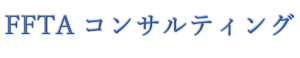HSの解釈に関する通則5は、物品を収納するケース、容器、包装材料のHSコード上の取扱いに関する規則です。
(a)長期の使用に適する専用ケース、収納容器に関する規則
及び
(b)その他の容器、包装材料に関する規則
の2つの規則からなりますが、(a)の規定が(b)の規定に優先して適用されます。
前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
(b)(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
目次
通則5(a) 専用ケース、収納容器等の取扱い
この通則5(a)は、次の全てに該当する容器については、容器(ケース)に収納されている物品の属する項に一体として分類されることを規定しています。
- 特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させた容器(容器によっては、収納する物品の形状に合わせて製作されているものもある。)
- 長期間の使用に適する容器(収納される物品の耐久性に合わせて製作されている。また、これらの容器は、当該物品が使用されない時(例えば、輸送、貯蔵等の期間)は、これを保護する役目がある。)
- 輸送の便宜のため収納される物品と別々に包装されているかいないかを問わず、収納される物品とともに提示される容器
- 通常収納される物品とともに販売される容器
- 重要な特性を全体に与えない容器
収納される物品とは別個に容器だけを通関する場合は、その容器の属する項に分類されます。例えばバイオリンを収納する容器だけを通関する場合は第42.02項に分類されます。
通則5(a)の適用事例
収納される物品とともに提示される容器で、この通則の規定を適用してその所属が決定される容器の例には、次のような物品があり、それぞれ収納されている物品と共に分類されます。
- 身辺用細貨類の箱及びケース ⇒ 身辺用細貨類と共に分類(71.13)
- 電気かみそりのケース ⇒ 電気かみそりと共に分類(85.10)
- 双眼鏡のケース及び望遠鏡のケース ⇒ 双眼鏡及び望遠鏡と共に分類(90.05)
- 楽器のケース、箱及びバッグ ⇒ 楽器と共に分類(例えば92.02)
- 銃のケース ⇒ 銃と共に分類(例えば93.03)
通則5(a)の適用除外
この通則が適用されない容器の例としては次のようなものがあります。
- 茶を入れた銀製の茶筒
- ウイスキーを入れた装飾的な陶磁製入れ物
これらは、中に入れる商品に比べ容器にも重要な特性があると考えられます。このような場合、通常、中身と容器は別々に分類し、課税されます。税関では、このように中身と容器を別々に分類して課税することを「分離課税」と呼んでいます。
通則5(b) その他の包装材料及び包装容器の取扱い
この通則5(b)は、物品を包装するために通常使用される包装材料及び包装容器は、収納されている物品の属する項に一体として分類されることを規定しています。例えば衣類を段ボールに収納している場合は、段ボールは衣類の属する項に一体として分類されます。
通則5(a)は通則5(b)に優先します。したがって、通則5(a)に記載されているようなケース、箱及びこれらに類する容器の所属は、通則5(a)を適用して決定します。
通則5(b)の適用事例
通則5(b)が適用される事例としては次のようなものがあります。
1.ツナの缶詰:缶はツナと共に第16.04項に分類する
2.ボトルワイン:ワインのボトルは、ワインとともに第22.04項に分類する
3.殺虫スプレー:スプレー缶は殺虫剤とともに第38.08項に分類する
4.箱に入った革靴(本底が革):箱は革靴とともに第64.03項に分類する
通則5(b)の適用除外
圧縮ガス用の金属製のボンベ、リタナーブルコンテナ(通い箱)など、明らかに反復使用に適するような包装材料及び包装容器には通則5(b)は適用されません。これらの容器は、通常、分離課税の対象となります。
これらの容器は通則5(a)の条件を満たさないことにご注意ください。
日本への輸入の際は関税定率法第14条第11号(再輸入免税)や第17条第2号及び第3号(再輸出免税)の対象となる可能性がありますので、関税有税の場合などは税関に事前に相談してみると良いと思います。
原材料・部品のHSコードの管理にお困りではありませんか?
多数の原材料・部品のHSコードを管理をしていくことは大変です。
FFTAコンサルティングではHSコードの専門家として、貴社の製品及び原材料のHSコード表の作成及び管理を支援いたします。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。