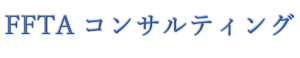「メーカー指定のHS番号に誤りがある理由」のページで、メーカーのHSコードに誤りが散見されること、また、EPA原産地証明の基礎資料となる原材料表のHSコードにも誤りが多いことを指摘しました。また、その理由として、関税率表解説を見ていないことによる基礎的な間違いが多いことも指摘しました。
輸出入しようとする貨物に正しいHSコードを付すためには、関税率表解説(Explanatory Notes)の規定を確認することが大変重要です。正しいHS分類を行うために関税率表解説の読み方を解説します。さらに、分類例規(Claddification Opinions)の活用方法についても解説します。
目次
「関税率表解説(Explanatory Notes)」とは
関税率表解説は、HS条約を管理している世界税関機構(WCO)が、HS条約の付属書であるHS品目表の公式解釈をまとめた「Explanatory Notes」を日本語に翻訳したものです。法的な位置付けは、Explanatory NotesがWCOの勧告、関税率表解説は財務省関税局長通達です。
Explanatory NotesがWCOの勧告ということは、HSの分類について、締約国はExplanatory Notesの規定に拘束されることになります。日本では、Explanatory Notesの改正が行われた際には、数か月遅れで関税率表解説を改正しています。この期間のずれは、日本語に翻訳する手間暇等を考えるとやむ得ないことと思われます。
各国の税関ではHS品目表とExplanatory Notesの規定に従って輸出入される品目について、HS品目表のどの項目に該当するかの分類(注)を行います。日本の税関でも同様に関税率表解説に従って輸出入品の関税分類を行っています。関税率表解説、Explanatory Notesは、HS分類のバイブルともいえるものです。
(注)以下、個々の商品・貨物にHSコードを付していく作業を「HS分類」、「関税分類」といいます。というのも、個々の商品・貨物にHSコードを付すという作業は、HSの1,228の項及び5,612の号(何れも2022年版HS)のどれか一つに分類を行っていく作業に他ならなず、また、その結果として関税率が決定されることとなるためです。
関税率表解説及びExplanatory Notesの入手
税関ホームページに関税率表解説が掲載されていますので、誰でも見ることができます。冊子版が必要な方は、日本関税協会から発売されていますので、お問合せください。
Explanatory NotesはWCOから発売されています。冊子版の他、Explanatory Notesを含めた、有料のオンラインデータベースのサービス(英語、フランス語、スペイン語)もWCOで提供しています。日本関税協会でも購入の斡旋を行っているようです。
関税率表解説の読み方
関税率表解説の構成
関税率表解説は、HS品目表の構成に準じて作成されています。
冒頭に「関税率表の解釈に関する通則」についての解説が掲載されています。本ホームページの通則についての記事もこの解説の規定に沿ったものです。
次に部注が掲載されています。その次に、部注及び部全体に及ぶ号注の規定を解説した、「総説」が掲載されています。部注のない部や総説が掲載されていない部もあります。
部と同様の構成で、類(HS2桁)の類注、号注及び類の総説が掲載されています。
次に各項毎の解説が掲載されています。一部の号を除き、号の解説は掲載されていません。

総説
部及び類に分類される物品及び分類されない物品を概括的に記述し、また、部注、類注及び号注の規定を解説した部分が「総説」です。第1部のように総説が掲載されていない部もあります。
また、第11部の繊維製品については、部の総説は20ページもわたる長大なものです。この総説の規定を理解しないと繊維製品の正確な分類を行うことは困難と言えるでしょう。
本ホームページの解説記事も部及び類の総説に沿ったものです。部及び類の総説を頭にいれた上で各項の解説の規定を読まないと誤った分類になることもあるので注意しましょう。
「メーカー指定のHSコードに誤りがある理由」の所でも触れましたが、メーカーのHSコードの誤りの多くが部注、類注の規定の無視又は理解不足によるものです。
項の解説
類の総説の次に各項(HS4桁)の解説が掲載されています。
各項の解説の冒頭には、各項に分類される号が掲載されています。
項のテキストの用語の定義や項がカバーする物品の範囲、項に分類される物品の製造方法等についての解説がなされています。分類しようとしてる物品が解説の規定に合致しているか否か検討を行います。
多種類の物品が分類される項では、その項に分類される物品をいくつかのカテゴリーに分けて解説しています。号(HS6桁)の解説は通常明示的には掲載されていませんが、号の表現と項の解説のカテゴリーの表現が一致している場合は、そのカテゴリーに分類される物品が、号に分類される物品と考えてよいと思います。

号の解説
あまり多くありませんが、号の範囲を明確にするための解説が別途記載されている項もあります。その場合は、号の分類についてはその解説の規定に従い分類することとなります。

除外規定
総説や項の解説で、これらの一番最後に記載されている除外規定も重要です。(途中に記載されている箇所もあります。)
物品を分類する際に、項の規定からある項に目星を付けて解説を読んでいくと、最後に「この項には、次の物品を含まない。」と記されていて、分類しようとしている物品がこの除外規定に当てはまることも多いのです。この場合、通常、除外規定にはその物品が分類される項が記載されているので、もう一度、除外規定に記されている項の解説を調べることになります。
90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
第90.04項関税率表解説
(中略)
この項には、次の物品を含まない。
(a)コンタクトレンズ(90.01)
(b)眼鏡の形状に作ったオペラグラス、レーシンググラスその他これらに類する物品(90.05)
(c)がん具の眼鏡(95.03)
(d)カーニバル用品(95.05)
関税率表解説の活用事例(ホワイトチョコレートのHSコード)
砂糖を使用しないホワイトチョコレートの分類を考えてみます。
ホワイトチョコレートはカカオから出来ているので、18.06項の「チョコレートその他のココアを含有する調製食料品」に分類されるのではないかと考えたとします。ところが、18.06項の解説の最後に
この項には、次の物品を含まない。
(a)ホワイトチョコレート(ココアバター、砂糖及び粉乳から成る。)(17.04)
(略)
と規定されており、ホワイトチョコレートはチョコレート菓子ではなく、第17.04項の砂糖菓子に分類されることが分かります。(この除外規定は、第18類注2「第 18.06 項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。」に基づくものです。)
ここで念のため、第17.04項を見てみます。第17.04項の規定は「砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)」となっており、さらに第17.04項の関税率表解説には、
(ⅵ)砂糖、カカオ脂、粉乳及び芳香剤から成り、ココアを極く微量にしか含有していないホワイトチョコレート(カカオ脂はココアとはみなさない。)
とありますので、確かに通常のホワイトチョコレートは第17.04項に分類されることになります。
ところで、砂糖の代わりにソルビトール等の人工甘味料を使用しているホワイトチョコレートの場合はどうなるでしょう。第17.04項の関税率表解説の最後に記載されている除外規定には、
「この項には、次の物品を含まない。
(略)
(d)砂糖の代わりに人工甘味料(例えば、ソルビトール)を含有するスイート、ガムその他これらに類するもの(以下略)(21.06)
とあり、砂糖を含有しないホワイトチョコレートは第21.06項に分類されることが分かります。
分類例規
分類例規には、WCOの勧告である「Classification Opinions」を日本語に訳した国際分類例規と国内分類例規の2種類ありますが、両者とも財務省関税局長通達となっています。
分類例規は税関ホームページに関税率表解説とともに掲載されています。冊子版が必要な方は日本関税協会から出版されています。また、Classification OpinionsはWCOから販売されています。
国際分類例規は、国際的なHS分類を統一するうえで参考となる分類事例を例示したもので、HS委員会で決定された分類事例をもとに作成されたものです。国際分類例規には通常、通則のどの規定を利用して分類が決定されたか書かれています。
国内分類例規は我が国における分類基準及び分類事例がまとめられているものです。国内細分に関する分類基準が示されている部分もあります。