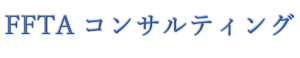(a)各項に記載するいずれかの物品には、①未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、②完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(b)各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従って決定する。
HS品目表の解釈に関する通則2
HSの解釈に関する通則2は実質的に次の3つの規則よりなると考えられます。
- 通則2(a) 未完成の物品の所属
- 通則2(a) 提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものの所属
- 通則2(b) 二以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属
なお、通則2(a)の規定は、第1類から第38類の物品には通常適用しません。
目次
- 通則2(a) 未完成の物品の所属
- 通則2(a) 提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものの所属
- 通則2(b) 二以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属
- 雑談コーナー ハーフカット車の関税分類問題
通則2(a) 未完成の物品の所属
通則2(a)の①の部分「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む」の規定は、項には完成品のほか、未完成のもので、提示の際に完成した物品としての重要な特性を有するものをも含めるようにするものです。
「未完成の完成品」という言葉もあります。この規定が適用される物品には次のようなカテゴリーのものがあります。
完成品としては一部が欠落している物品
完成品としては一部が欠落している物品であっても、完成品として重要な特性を有している場合には完成品と同じHSコードに分類されます。これらには次ような物品があります。
- 袖が縫い付けられていない編物のセーター(第61.10項)
- エンジンの付いていない乗用自動車(第87.03項)
- 車輪が取り付けられていない自転車(第87.12項)
完成品のブランク
項のテキストに「ブランク」と書かれていない場合、ブランクは完成品と同じ項に分類します。「ブランク」とは、そのまま直接使用することはできませんが、完成した物品又は部分品のおおよその形状又は輪郭を有し、かつ、例外的な場合を除き、完成した物品又は部分品に仕上げるためにのみ使用する物品をいいます。
これらには次ような物品があります。
- ペットボトルのブランク
⇒ ペットボトルの成形前の中間生産品(管状で一端が閉じており、口の方はネジ式の蓋を取り付けるためにネジが切られている。ネジ切り部より下の部分は、所定の大きさや形に膨張させる。膨らませただけでペットボトルが完成する。)は、ペットボトルのブランクとして第39.23項分類される。 - のこぎりのブレードのブランク
⇒ のこ歯を有する限り、帯状のもの及びディスク(駆動軸にディスクを取り付けるための中心に穴があるもの)は、のこぎりのブレードのブランクとして第82.02項に分類される。
完成した物品としての重要な形状を有するに至っていない半製品(通常、棒、ディスク、管等の形状のもので、特定用途に適した加工がなされていないもの。)は、「ブランク」としては取り扱いません。
通則2(a)を適用しない事例
通則1の後段には、「これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。」とされています。従って、未完の完成品の分類について項又は類に規定がある場合には、この通則2(a)の規定は適用されません。
例えば、下記のボールベアリング用の未研摩の鋼球の分類です。
ボールベアリング用の未研摩の鋼球HSコード
磨き鋼球のHSコードについては、第84類注7に次の規定があります。
第84.82 項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が0.05 ミリメートル以下で、かつ、1%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第73.26 項に属する。
ボールベアリング用の鋼球は玉軸受(ボールベアリング)の部分品として第8482.91号に分類されます。ボールベアリングに使用する鋼球用の物品で、この注の精度に満たないものは第73.26項に分類されることとなっており、通則2(a)は適用されません。
また、この注の規定の精度を満たすものは、ボールベアリングに使用しない鋼球(例:ボールペン用の鋼球)であっても、第8482.91号に分類されることとなります。
通則2(a) 提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものの所属
通則2(a)の後段の②の「完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるもの」の規定は、完成した物品で提示の際に組み立ててないもの又は分解してあるものは、完成した物品と同一のHSコードとなることを定めたものです。
このような状態で物品が提示されるのは、通常、包装、荷扱い又は輸送上の必要性、その他の理由によります。
- 縫製されていない綿織物製のワンピース(第62.04項)
- コンプリートノックダウンの乗用車(第87.03項)
- 組立てられていない自転車(87.12項)
- 組立てていない木製のタンス(第94.03項)
この通則の適用上、「提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるもの」とは、組立て操作のみを伴うもので、例えば、締付具(ねじ、ナット、ボルト等)又は鋲接若しくは溶接により構成要素を組み立てれば完成品になるものをいいます。この場合において、組立方法の複雑さは考慮しません。なお、当該構成要素には、完成された状態にするための更なる作業操作は施されません。完成品に組み立てる上で必要となる数を超える余分な構成要素は切り離してその所属を決定します。
プラント貨物などの場合、輸送の都合等で分割して船積みされる場合がありますが、このような場合に対する通則2(a)の適用については、「プラントのHS分類の簡素化-通則2(a)と機能ユニット」のページをご参照ください。
未完成の完成品と組立てていない物品の両方の規定が適用される事例
この通則は、未完成の物品(上記の「未完成の物品の所属」の規定により完成したものと同じ項に属するものに限る。)で、提示の際に組み立ててないもの又は分解してあるものについても適用します。例えば次のような事例です。
- 縫製されていない綿織物製の男子用ワイシャツで襟の部分が欠落しているもの(第62.05項)
- セミノックダウンの乗用自動車(組立てた場合、乗用自動車として重要な特性を有すると認められるも。)(第87.03項)
- 車輪が取り付けられていない自転車で自転車の形に組立てられていないもの(87.12項)
通則2(b) 二以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属
通則2(b)は、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品及び二以上の材料又は物質から成る物品に関する規定です。この通則が適用される項は、材料又は物質が記載されてある項(例えば、象牙(第05.07 項))及び特定の材料又は物質から成る物品であることを示す記載のある項(例えば、天然コルクの製品(45.03 項))です。
この通則の効果は、ある材料又は物質について記載した項の範囲を拡大して、各項には当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むようにすることです。
(例)
- ブドウ果汁に発酵防止の亜硫酸ガスを加えたもの
⇒ ブドウ果汁として第20.09項に分類 - 天然コルクにプラスチックのキャップを取り付けた栓
⇒ 天然コルクの製品として第45.03項に分類 - プラスチックのシートと紙を貼り合わせた物品
⇒ プラスチックのシートと紙のどちらに特性があるかにより第39類又は第48類に分類
*牛乳パックの紙(紙の両面がポリエチレンシートで被覆されている。):第48.11項
*接着面に紙を貼り合わせたスマホの保護用プラスチックフィルム:第39類
材料又は物質から成る物品が、この通則を適用した結果、二以上の項に属するとみられる場合には、通則3の原則に従って所属を決定します。
通則2(b)を適用しない場合
通則2(b)は、項の規定に該当しない物品までも含むように項の範囲を拡大するものではありません。この通則は、項又は部注、類注に別段の規定がある場合には適用されません。
(例)
- 第15.03 項のラード油は「混合してないもの」と定められており、他の物質を混合したラード油は分類されない旨規定されているので、通則2(b)は適用されません。
- ビール(第22.03項)とワイン(第22.04項)からなるカクテルは通則2(b)は適用されず、第22.06項の「発酵酒の混合物」に分類されれます。
- 人造コランダム(第28.18項)を接着剤(第35.06項)で板紙(第48.04項)に付着させた研磨紙
第68.05項には「粒状の人造の研磨材料を板紙に付着させた物品」が分類されると規定されており、通則2(b)は適用されず、第68.05項に分類されます。
雑談コーナー:ハーフカット車の関税分類問題
ハーフカット車と言っても何かわからない方も多いのではないかと思います。ハーフカット車とは、文字通り、車を前の部分と後ろの部分に半分に切断した車です。
税関に勤務していた頃、開発途上国の税関職員と話をしていると、このハーフカット車の関税分類問題で盛り上がることがありました。一般に途上国では、完成車の関税が非常に高く、それに比べて自動車部品の関税は低率となっている場合が多いようです。中古の完成車を輸入すると高額の関税の支払いが必要になるので、車を半分にカットし、前の部分と後ろの部分を車の部品として別々に輸入し、輸入後に両者を接合して高額の関税を免れようとするものだそうです。
半分にカットした車を輸入後に再びくっつけて本当に安全性は大丈夫なのかと心配になりますが、私が北海道の小樽港で見たハーフカット車は丁寧にカットしてあったので、多分、大丈夫なのでしょう。

しかし、後ろの部分だけ、前の部分だけしか提示されなければ、何れの部分も車としての重要な特性は有していないので、通則2(a)の適用は難しいと思われます。国際分類例規では、ハーフカット車は自動車の部分品として第8708.99号に分類される旨規定されています。
さて、このハーフカット車を前の部分と後ろの部分を一体で税関に提示されれば、通則2(a)を適用して完成車として分類することとなるのでしょうか?
小樽港の事例では、適当に半分にカットした車もありました。途上国では、中古の部品の需要も多いので、実際にハーフカット車を輸入して、中古の部品取りをする場合が多いということも、余計に途上国の税関の対応を難しくしています。
輸入時の形状を物理的に誤魔化して、高額の関税を免れようとするのはどこの国にもあることです。開発途上国の税関職員がどのようにしてハーフカット車の問題に対応しているかは結局よくわかりませんでしたが、日本でも、コンニャク粉とグラニュ糖を混合して輸入申告し、通関後に分離するといったようなことが行われていました。このため、税関から「二種類以上の物品を混合した物品で輸入後その構成物品に分離する可能性があるものの取扱いについて」という通知が出されています。