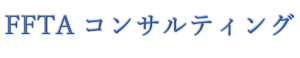HSの解釈に関する通則1は、物品の分類は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って行うことを規定しており、関税分類を行う上での大原則です。
HS品目表の項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定は条約そのもの、その品目表を翻訳した「関税率表別表」は法律そのものですので、これらの規定に従い関税分類を行っていく必要があります。
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
目次
部・類・節の表題について
HS品目表は、全ての商品を部、類及び節に区分し、それぞれにできるだけ簡明な表題が付されています。しかしながら、多くの場合、部及び類に含まれる商品をすべて表題に含めることも、また、特定して列挙することも不可能です。そのため、通則1の冒頭で、部、類及び節の表題は「単に参照上の便宜のために設けたものである」ことを明記しています。例えば、次の事例のように類の表題と実際の分類が異なっている物品が多数あります。
- 塩化カリウム(31.04項)
31類注4には、塩化カリウムは純粋であるかどうかにかかわらず、31類(肥料)に分類されること、28類注3には、28類(無機化合物)に分類されないことが規定されている。 - 食用の牛の胃・腸(ミノ、センマイ、ホルモン)(05.04項)
牛の胃・腸は2類(肉及び食用のくず肉)には分類されず、項に特掲されている5類(その他の動物性生産品)の05.04項に分類される。ただし、くず肉でも、タン(舌)、レバー(肝臓)、ハツ(心臓)、マメ(腎臓)、フクロ(肺)等は02.06項のくず肉に分類される。
項の規定・部注又は類注の規定に従い項を決定する
HSコードを決定する際には、項の規定及びこれに関係する部注又は類注の規定に従うこととされています。従って、まず最初に項(4桁のHSコード)を決定します。項が決定できないと、HSコードの2ケタ(部・類)は決定できません。
大部分の物品は通則1を用いて分類決定を行うことができます。国際分類例規には、どの通則を使用して分類が決定されたか記載されていますが、多くは通則1が適用されています。
項の規定
HSコード4桁の番号を項と言います。(詳しくは、こちら)
項の規定は、実行関税率表、輸出統計品目表の4桁の番号の次に記載されています。
関税率表解説にも表題として記載されています。

部注・類注
部注・類注は、税関ホームページの輸出統計品目表及び実行関税率表に掲載されています。
また、関税率表解説にも部及び類の冒頭に掲載されています。関税率表解説を参照すると、次に「総説」があるので、注の解釈も示されていて参考になります。
部注・類注の役割
部注及び類注には次のような役割があります。
部注及び類注で定義された用語や基準値は必ずしも関連業界の定義や基準とは一致しているとは限らないので注意が必要です。
部又は類から除外される物品を明確にする
多くの部及び類の冒頭に「この部(類)にはXXを含まない。」という、部又は類から除外する物品を明示しています。
第45類(コルク及びその製品)注1は次のように規定されています。
この類には、次の物品を含まない。
(a)第 64 類の履物及びその部分品
(b)第 65 類の帽子及びその部分品
(c)第 95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
この規定により、コルク製の履物、帽子、玩具等は、コルク製品として第45類には分類されず、それぞれ、履物、帽子、玩具等として分類されることを規定しています。
部又は類に分類される物品の範囲を明確にする
部又は類に分類される物品を明確にするための注です。
例えば、第1部(動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品)の注1には次のように規定されています。
この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
この規定により、牛(01.02)及び牛肉(第2類)には、成牛の他小牛も含まれることを明確にしています。
HS品目表を通して使用されている用語を定義する
HS品目表で規定されている使用されている用語を定義するための注です。
例えば、第39類注1では、HS品目表における「プラスチック」の定義が定められています。
この表において「プラスチック」とは、第 39.01 項から第 39.14 項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第 11 部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
最初に「この表において」とされていることから、この注の「プラスチック」の定義はHS品目表で「プラスチック」と書かれている言葉全てに適用されることを示しています。
後段の定義では、人造繊維等の紡織用繊維は、例えプラスチックと同じ化学的な組成・性質を持つものであっても、「プラスチック」とは見做さないことを規定しています。
部又は類で使用されている用語を定義する
上記の「プラスチック」の定義は「この表において」とされていますので、HS品目表全てに適用されますが、ある特定の部又は類にのみ適用される定義が規定されているものもあります。
例えば、「ペレット」という言葉は、第2類(魚類)と第2部(植物性生産品)及び第4部(調製食料品等)では異なる定義となっています。
この類において、「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第3類注2
この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第2部注1、第4部注1
特定の項で使用される用語を定義する
特定の項で使用される用語を定義するための注もあります。
例えば、第22.02項に「アルコールを含有しない飲料」という言葉が使用されていますが、この言葉の定義が第22類注3に規定されています。
第 22.02 項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が 0.5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第 22.03 項から第 22.06 項まで又は第 22.08 項に属する。
第22類注3
日本の酒税法第2条では酒類とは「アルコール分が1度以上の飲料」と規定されています。従って、アルコール分が0.5%~1%の飲料は、関税の分類(HSコード)の世界では酒類として取扱われますが、酒税法上では酒ではなくノンアルコール飲料として取扱われることとなります。
特定の項に分類される物品を規定する
特定の項に分類される物品を規定する注もあります。
たとえば、第31.04項の規定は、「カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)」となっています。しかし、第31類注4では、この項に含まれる物品は次のものに限定される旨規定されています。
第 31.04 項には次の物品(第 31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a)次のいずれかに該当する物品(ⅰ)天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
(ⅱ)塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
(ⅲ)硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅳ)硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)(b)(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
第31類注4
項と項の分類基準を明確にする
似たような物品で2つ以上の項が該当する恐れがある場合には、部注・類注でその分類基準を明確にしている注があります。例えば、同じ四角形の織物から出来ているハンカチとスカーフを区分するために第62類注8が設けられています。
一辺が55センチメートルの正方形の織物は、例えスカーフとして製造されているとしても、この規定によりハンカチとして第62.13項に分類されることとなります。
スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが60 センチメートル以下のものは、ハンカチとして第 62.13 項に属する。ハンカチで1辺の長さが 60 センチメートルを超えるものは第 62.14 項に属する。
第62類注8
項又は注に別段の定めがある場合
「これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか」とは、通則2から通則4に先立って、注又は項の規定が適用されることを示しています。HSコードを決定する際には、項又は注の規定に従い、まず4桁の項の番号を決定することを規定しています。
例えば、第31類(肥料)注4にはカリ肥料の定義が定められています。この定義により、塩化カリウムと硫酸カリウムを混合した肥料は第31.04項に分類されますが、硫酸カリウムと硫酸アンモニウムを混合した肥料を、通則2(b)の規定を適用し、項の範囲を拡大して第31.04項に分類することはできないことを示しています。
通則1では分類が決定できない場合
通則1では分類を決定できない場合、例えば2以上の構成要素からなる物品や2以上の項に分類される可能性があるため、物品の所属を決定できない場合など、必要に応じ通則2、3、4又は5の原則に従って分類を行います。
通則2(a)の規定は、未完成の物品や提示の際に組み立ててない物品及び分解してある物品に対する規定であり、通則⓶(a)の規定が満たされており、かつ項又は注に別段の定めがない場合には完成した物品としてHSコードを決定することとなっています。
- 通則2 未完成の完成品、2以上の物質からなる物品の分類
- 通則3 二以上の項に属すると みられる場合の分類
- 通則4 どの項にも該当しない物品の分類
- 通則5 ケース、容器、包装材料の取扱い
- 通則6 号の分類
サプライヤー証明のコンサルティング
⇒貿易に馴染みが無くても、大丈夫。丁寧に対応いたします
*サプライヤー証明書の内容が正しいかどうか第三者の立場でチェックをしてほしい
⇒ご安心ください。内容チェックのため知りえたサプライヤー様の企業秘密は洩らしません。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。